ブランクとゴールの『ルイーズ』 [オペラ録音・映像鑑賞記]
 シャルパンティエの『ルイーズ』は労働者階級の娘が、両親の「お人形」であった状態から「人」として目覚めてゆく様を描いた歌劇。
シャルパンティエの『ルイーズ』は労働者階級の娘が、両親の「お人形」であった状態から「人」として目覚めてゆく様を描いた歌劇。初演は1900年の2月。
フランス初のウ゛ェリズモ風オペラと言われていますが、女性を旧い価値観から開放したシャネルがパリのカルボン通りに帽子店を開いたのが1910年であることを考えますと、他のヴェリズモ作品群から頭ひとつ分飛びぬけて現代的な作品という感もあります。
(ちなみに、《今日からは"Depuis le jour"》聴きながらリブレットを目で追っていてパッと思い浮かんだ映画がナタリー・ウッドの『草原の輝き』ですが、こちらは1961年の公開です。)
ルイーズの「目覚め」は「旧時代からの脱皮」であり、貧困・享楽・諦観・自由のごった煮となった都市パリに象徴されています。二幕や三幕冒頭の街のシーンはさぞ圧巻なことでしょう。
そのパリの狂騒を苦々しく眺める旧時代の代表がルイーズのパパとママ。詩人の若者との愛と自由に生きようとするルイーズを「よい娘」の檻に閉じ込めようとする、両親の典型的な役割を担っています。
歌うはエルネスト・ブランクとリタ・ゴール。ワタシにとってのゴールデンコンビであり、ブランクとゴールそれぞれの持ち味がこの作品のテーマ固めに大きく貢献した、理想的なキャスティングではないかと、個人的に思っています。
御年59才のブランク先生、高音のみずみずしさは(微妙に)減少したような気もしますが、低音のセクシーさは相変わらず。以前、ブランクのあまりのセクシー歌唱に「パパ役禁止令」を発令したほどなのですが、この作品のように娘に精神的にベッタリした父親役であれば話は別です。ブランクのデレっとした声のセクシーさが、娘の側からみた親世代のうっとうしさをいや増して、大変効果的であると感じます。
なにしろ、
家出をした娘の部屋に跪いてむせび泣いたり(ママ談)、
娘恋しさで病気になったり(ママ談)、
一時的に顔を見せた娘に暴力的なまでに激しく抱きつき、長~い長~~~いキスをしたり、
あげくのはてには娘を膝にのっけて揺すりながら子守唄を歌ったりしちゃう、
エ~ロいエ~ロ~いパパなンですからッ!!(*´Д`)ヤ~ン
息子であれ娘であれ、子どもに対する親の束縛、過干渉には何かしら性的な臭いがつきまとうものであります。
リタ・ゴールのママも同様で、そもそもルイーズと恋人のジュリアンの関係に最初に反対しているのはママなのですが、そのママの態度も少しおかしい。ジュリアンがルイーズに囁いた愛の言葉を、さも馬鹿にしたように繰り返してみせたり、まるっきり冷静さを欠いています。ぶっちゃけ、性格悪そう。
おそらくママは、同じ女性として、愛と自由に生きようとする娘に嫉妬を感じているのでしょう。
一幕ではルイーズの家族の団欒シーンが繰り広げられますが、ふざけてママの腰を抱いて踊ろうとするパパを振り払うなど、結婚生活に対するこのママの冷めた思いを垣間見ることができます。
ルイーズをたしなめるパパの、
「Qui dit amoureux, toujours dit aveugle !(Whoever says he's in love,admits he is blind)」
というセリフにも、なんとなくこの熟年夫婦の微妙な距離感が見え隠れしています。
リタ・ゴールの、美しいけれども不感症っぽい声質と歌唱が、このママの内面に大変マッチしていると思うのです。
四幕の第2場~3場にかけての、ルイーズとパパ、ママの口論は圧巻です。哀願口調からみるみる荒れ狂っていくパパ。一幕での威勢の良さはどこへやら、オロオロするママ。パリの街の呼び声に応え、青春を歌いあげるルイーズ。
次第に情熱的にテンポを上げるワルツの調べには、19世紀から20世紀へ移り変わる時代のエネルギーが満ち溢れており、聴くたびにしばし言葉を失ってしまいます。私自身の感じる限り、21世紀の幕開けはこのような期待感は皆無だっただけに(既に自分が旧世代の人間だったってことでしょうかね……)。
最後になりましたが、ルイーズを歌うフェリシティ・ロットもたいへん良いです。この人の声はいつもうら若き娘らしく、とても可憐。
-------------------------------------
『Louise』/Gustave Charpentier
Sylvain Cambreling
Belgian National Opera Symphony Orchestra
Louise:Felicity Lott(S)
Julien:Jerome Pruett(T)
Le Pere:Ernest Blanc(Br)
La Mere:Rita Gorr(A)
トーマス・アレンの『魔笛』 [アレンの録音・映像鑑賞記]
そろそろブランク先生の『ルイーズ』と『清教徒』の感想を書きたいのですが、(ネタとして)中途半端なアレンの歌唱を聴かされたままではどうも寝つきがよくありません。
というわけで、パパゲーノ@『魔笛』です(`・ω・´) シャキーン
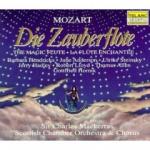
ワタシの苦手なジングシュピールですが、オレ様って歌も上手くてスットコドッコイな演技もできて、世界中から「カコイイ」って愛されちゃってるの♪と言わんばかりのオーラ(というか、菌)をふりまく、いつものアレンが楽しめます。
過剰なアクセント(with 音程はずし)、痰のからんだイガラっぽい呻り声、繊細なピアニッシモまたの名を囁き唱法などなど、こんな芸達者な兄さんじゃないと聴いた気がしないのサ。
ワタシの中でのパパゲーノ・スタンダードはワルター・ベリーなわけですが。
ベリーに比べると、アレンはやっぱ低音弱いし、何か「プクク…」とたくらんでいそうな印象は拭えませんけど(要するに、可愛げが足りないんだね)、あっけらかんとした歌いっぷりで結構似合っていると思います。
今更ですが、典型的なMozartianなんですね……この人は。ヴェルディの『マクベス』全曲録音探すの、諦めました。カバリエたんと重唱やってるハイライトでガマンします(´・ω・`)
ところで、この録音のザラストロはロバート・ロイド、パミーナはバーバラ・ヘンドリクスというのも嬉しいところです。
ワタシはどうもソプラノ歌手が苦手で、というのも、大抵のソプラノの声(一部のテノールも含む)を聴くと耳が本気で痛くなったり疲れてしまったりするからなんですが(オペラを聴く体質じゃないのかも)、ヘンドリクスの声は平気です。この人の声はハスキーでとっても魅力的。
「ソプラノが耳に合わないんなら夜の女王のアリアこそ駄目じゃん!?」
まぁ実際そうなんですが、この録音の女王はジューン・アンダーソンでして、彼女の声もキンキンしてないので大丈夫です。
ただ、ちょっと、最高音が「ヨイショ!」って感じで、微妙に惜しい。
というわけで、パパゲーノ@『魔笛』です(`・ω・´) シャキーン
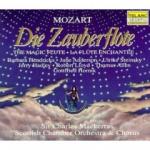
ワタシの苦手なジングシュピールですが、オレ様って歌も上手くてスットコドッコイな演技もできて、世界中から「カコイイ」って愛されちゃってるの♪と言わんばかりのオーラ(というか、菌)をふりまく、いつものアレンが楽しめます。
過剰なアクセント(with 音程はずし)、痰のからんだイガラっぽい呻り声、繊細なピアニッシモまたの名を囁き唱法などなど、こんな芸達者な兄さんじゃないと聴いた気がしないのサ。
ワタシの中でのパパゲーノ・スタンダードはワルター・ベリーなわけですが。
ベリーに比べると、アレンはやっぱ低音弱いし、何か「プクク…」とたくらんでいそうな印象は拭えませんけど(要するに、可愛げが足りないんだね)、あっけらかんとした歌いっぷりで結構似合っていると思います。
今更ですが、典型的なMozartianなんですね……この人は。ヴェルディの『マクベス』全曲録音探すの、諦めました。カバリエたんと重唱やってるハイライトでガマンします(´・ω・`)
ところで、この録音のザラストロはロバート・ロイド、パミーナはバーバラ・ヘンドリクスというのも嬉しいところです。
ワタシはどうもソプラノ歌手が苦手で、というのも、大抵のソプラノの声(一部のテノールも含む)を聴くと耳が本気で痛くなったり疲れてしまったりするからなんですが(オペラを聴く体質じゃないのかも)、ヘンドリクスの声は平気です。この人の声はハスキーでとっても魅力的。
「ソプラノが耳に合わないんなら夜の女王のアリアこそ駄目じゃん!?」
まぁ実際そうなんですが、この録音の女王はジューン・アンダーソンでして、彼女の声もキンキンしてないので大丈夫です。
ただ、ちょっと、最高音が「ヨイショ!」って感じで、微妙に惜しい。
トーマス・アレンの『コシ・ファン・トゥッテ』@ラトル盤 [アレンの録音・映像鑑賞記]
気持ちを奮い立たせるために購入した兄さんの去年の“コジ”DVDですが、1幕で撃沈されたまま続きを観る気が起こりません。演出があまり好みでない上、兄さんの声が出なさすぎです。調子の悪い兄さん映像には既に慣れっこになってしまいましたが、さすがにあれは……orz
まぁ逆の意味で渡英気分が更に高まったので当初の目的は果たせたわけですが、お蔵入り寸前のDVDはどうすればいいんでしょーか。
高かったんだぜ。金カエセ~ヽ(`Д´)ノ(←頑張って観れば済むことです)
 仕方ないのでCDでガマンする。こちらは96年のラトル盤で、もちろんアレンはアルフォンソ。10年前の録音なので、声もまぁまぁというところ。
仕方ないのでCDでガマンする。こちらは96年のラトル盤で、もちろんアレンはアルフォンソ。10年前の録音なので、声もまぁまぁというところ。
ですが、コレも微妙に不完全燃焼なCDなんですよ。いやご本人はどうだか知らないけれども、ファンとしては聴いていて物足りない。器用さと余裕が感じられるし、洒落臭ぇ歌唱も30~40代の頃と変わらないのだけれども。
ネタにするほどのオモシロ歌唱じゃないからですかね。鑑賞前に「アレンを聴くゾ~!!」と入れた気合が軽~く裏切られた気分になってしまうのですよ。私も基本的には、オペラには「大声」を期待しているので、そういう意味では兄さんには裏切られっぱなしです。
なんというか、アレンをアレンたらしめている(?)ガツガツした様子が少ないんですかねぇ。有名テノールを押しのけて主役ヅラしてやろうとか、オペラ歌手並みの大声を出そうと目玉が飛び出そうなくらいムキになるとか。そういうやんちゃなイメージが年をとるにつれてなくなりつつあるような。
聴いていてちょっとカチンとくるようなナルシ歌唱がこの人の持ち味なんだと思うのですが……。少なくともこのCDではあまり暴れず、お利口さんに聴こえるアレンなのです。
グリエルモがアルフォンソになり、兄さんもジイさんになっちゃったって感じですか(そういや、孫が4人もいるんですと)。
まぁ歌が上手いからいっか。
今年のアルフォンソはどうなんでしょうか。去年のDVDを観る限りでは、「声さえまともに出てくれれば何でもいい」って思っちゃいますケド。
(生でハラハラすることこそ兄さんファンの醍醐味、という説もありますな)
まぁ逆の意味で渡英気分が更に高まったので当初の目的は果たせたわけですが、お蔵入り寸前のDVDはどうすればいいんでしょーか。
高かったんだぜ。金カエセ~ヽ(`Д´)ノ(←頑張って観れば済むことです)
 仕方ないのでCDでガマンする。こちらは96年のラトル盤で、もちろんアレンはアルフォンソ。10年前の録音なので、声もまぁまぁというところ。
仕方ないのでCDでガマンする。こちらは96年のラトル盤で、もちろんアレンはアルフォンソ。10年前の録音なので、声もまぁまぁというところ。ですが、コレも微妙に不完全燃焼なCDなんですよ。いやご本人はどうだか知らないけれども、ファンとしては聴いていて物足りない。器用さと余裕が感じられるし、洒落臭ぇ歌唱も30~40代の頃と変わらないのだけれども。
ネタにするほどのオモシロ歌唱じゃないからですかね。鑑賞前に「アレンを聴くゾ~!!」と入れた気合が軽~く裏切られた気分になってしまうのですよ。
なんというか、アレンをアレンたらしめている(?)ガツガツした様子が少ないんですかねぇ。有名テノールを押しのけて主役ヅラしてやろうとか、
聴いていてちょっとカチンとくるようなナルシ歌唱がこの人の持ち味なんだと思うのですが……。少なくともこのCDではあまり暴れず、お利口さんに聴こえるアレンなのです。
グリエルモがアルフォンソになり、兄さんもジイさんになっちゃったって感じですか(そういや、孫が4人もいるんですと)。
まぁ歌が上手いからいっか。
今年のアルフォンソはどうなんでしょうか。去年のDVDを観る限りでは、「声さえまともに出てくれれば何でもいい」って思っちゃいますケド。
(生でハラハラすることこそ兄さんファンの醍醐味、という説もありますな)
トーマス・アレンの『道化師』 [アレンの録音・映像鑑賞記]
『道化師』といったらトニオ。
けど、アレンはシルウ゛ィオしか歌えない~という屈辱の演目(笑)
これがブランク先生なら「むしろシルウ゛ィオを…(*´Д`)」とジタバタしちゃうところなんですが(注:先生はデビューからしてトニオです)。
だってトニオってオイシイ役だし。本当は兄さんが「ばーちぃ!!」とみっともなく暴れてネッダに鞭でぶたれる音を聴いてみたい管理人です。
見損なったぞ、アレンヽ(`Д´)ノ 結局、二枚目路線は捨てられないのかっ。
などと盛大にツンデレぶりを発揮しつつ鑑賞。
……なにげに良い演奏なのです。ムーティの指揮、ドラマチックでカッコいいし。太鼓の音デカイし。
ネッダはレナータ・スコット。カニオはカレーラスですし、兄さん、共演者には常に恵まれていますな。
そして早くもシルウ゛ィオ登場。
声、小さっ……! というのはこのCDに始まったことではないのでいいとして、何なのだ、そのあからさまにフェロモン全開なウ゛ィブラートは!?
ブランク先生のようなセクシーさは感じませんが、情熱的で、ぶっちゃけ、ヤラしい。
“田舎町の若者”にしては洒落臭いし、誠実そうなイメージは皆無ですが(駆け落ちしても数ヶ月でネッダを捨てそう)、なかなかにお熱い求愛ぶりなのですよ。
やっぱアレンはアレだわ、得意げにロッシーニとか技巧的でノリノリなのも歌ってますが、本来はこういう“情感たっぷり歌い上げ系”に向いている歌手なんですね。正直、こんなに魅力的なシルウ゛ィオは初めてです。
うむむむ……これじゃまるでラブシーンやってるみたいじゃないですか(←つうか、ココはラブシーンです)。
……普通にドキドキしてしまいました……orz(←屈辱)
ところで、兄さんからトニオ役を奪ったカリ・ヌルメーラですが、倍音少なめなイイ声の歌い手でした。
プロローグの「Si puo? Si puo?」はちょっと小賢しく、幕が上がってからは地声を棒読み調に張り上げるなどして、ワタシにとっては理想的なトニオを演じています。「ばーちぃ!」はもっと大騒ぎしてくれてもいいけどね。
けど、アレンはシルウ゛ィオしか歌えない~という屈辱の演目(笑)
これがブランク先生なら「むしろシルウ゛ィオを…(*´Д`)」とジタバタしちゃうところなんですが(注:先生はデビューからしてトニオです)。
だってトニオってオイシイ役だし。本当は兄さんが「ばーちぃ!!」とみっともなく暴れてネッダに鞭でぶたれる音を聴いてみたい管理人です。
見損なったぞ、アレンヽ(`Д´)ノ 結局、二枚目路線は捨てられないのかっ。
などと盛大にツンデレぶりを発揮しつつ鑑賞。
……なにげに良い演奏なのです。ムーティの指揮、ドラマチックでカッコいいし。太鼓の音デカイし。
ネッダはレナータ・スコット。カニオはカレーラスですし、兄さん、共演者には常に恵まれていますな。
そして早くもシルウ゛ィオ登場。
声、小さっ……! というのはこのCDに始まったことではないのでいいとして、何なのだ、そのあからさまにフェロモン全開なウ゛ィブラートは!?
ブランク先生のようなセクシーさは感じませんが、情熱的で、ぶっちゃけ、ヤラしい。
“田舎町の若者”にしては洒落臭いし、誠実そうなイメージは皆無ですが(駆け落ちしても数ヶ月でネッダを捨てそう)、なかなかにお熱い求愛ぶりなのですよ。
やっぱアレンはアレだわ、得意げにロッシーニとか技巧的でノリノリなのも歌ってますが、本来はこういう“情感たっぷり歌い上げ系”に向いている歌手なんですね。正直、こんなに魅力的なシルウ゛ィオは初めてです。
うむむむ……これじゃまるでラブシーンやってるみたいじゃないですか(←つうか、ココはラブシーンです)。
……普通にドキドキしてしまいました……orz(←屈辱)
ところで、兄さんからトニオ役を奪ったカリ・ヌルメーラですが、倍音少なめなイイ声の歌い手でした。
プロローグの「Si puo? Si puo?」はちょっと小賢しく、幕が上がってからは地声を棒読み調に張り上げるなどして、ワタシにとっては理想的なトニオを演じています。「ばーちぃ!」はもっと大騒ぎしてくれてもいいけどね。
エーベルハルト・ヴェヒターの『ドン・ジョヴァンニ』・および、バリトンかバスかという問題 [オペラ録音・映像鑑賞記]
エーベルハルト・ヴェヒターの『ドン・ジョヴァンニ』を聴きました。
ヴェヒターも高めのバリトンですね。FDとよく似たドイツ的(?)な歌唱が微妙に気になりますが、底抜けに陽気で、どこか呑気なところもある“ナンパ師”といったキャラクターが好印象。
そういえば、この作品について、私が子どもの頃に抱いていたイメージには、こういうブッファ的な色合いが濃かったように思います。アンナが登場するとちょっと悲劇的な空気になるけど、それ以外ではエルヴィラ、レポレッロを相手にドタバタ、ドタバタ。
ところが、ラストの石像の登場で、物語は一気に暗転する。その劇的な展開に度肝を抜かれたものでした。
なので、幕開けから一貫して不吉な雰囲気を漂わせる演奏や演出は、実はあまり好みではありません。demonicなドン・ジョヴァンニも、試みとしてはおもしろいとは思いますが、レポレッロと早口でまくしたてる旋律がキャラと合わないので、イマイチ気持ちが入っていかないのですね。
というわけで、ドンジョはつやつやしたバリトン希望。バスでも声が明るきゃいいですが、要所要所でずっしりと重く響きますので、軽薄なドンジョのイメージからはちょっとズレてしまいます。
立派なバス声は、クライマックスで石像が聞かせてくれるからいいんデス。
ドンジョに高めのバリトンを望むのは、このクライマックスでの三重唱(ジョヴァンニ、石像、レポレッロ)が最大の“萌えポイント”だからなんですね。
クライマックスの直前まで、華やかで生命力にあふれたパートを歌っているドン・ジョヴァンニ。ところが、石像の登場とともに重厚で不吉な和音に押さえつけられ、たちどころに身動きがとれなくなります。このオペラ全体の楽曲の進行を支配し、操っていた権力が、主人公のジョバンニから石像に移るわけです。
「Parlo: ascolta! piu tempo non ho! (I will speak. Listen. My time is short!)」
と歌う石像のパートが、ティンパニ付きの、大音響の管弦楽に後押しされているのに対し、
「Parla, parla, ascoltando ti sto, (Speak then, for I am listening,)」
ジョバンニのパートの伴奏は弱々しい弦楽器と木管だけ。
うわ言のようなレポレッロのパートでさえ、2回目は石像のパートのほうに重なっていますので、この部分でのジョバンニは、どんなに気丈そうな歌唱であっても、哀れで、処刑台の前に独り立たされた者のような危うさが感じられると思うのです(モーツァルトって、やっぱ凄い)。
「オトコが痛めつけられ憔悴する図」に萌えるワタシとしては、できればここで、石像とタイマン勝負してほしくない。意地を張ろうと強がろうと、声の力と迫力では圧倒的に石像に劣っていてもらいたい……というのが、ワタシの理想のジョヴァンニ像。ハイ・バリトンなら、そのような雰囲気は顕著に出やすい(と思います)。
ただでさえ石像に抵抗する部分のジョバンニの旋律はキーが低め。バス歌手ならキレイに発声できますが、これが例えばアレンだとちょっと嗄れて聴こえます。アレンに比べれば低めの音域も得意そうなヴェヒターも、この録音ではさほどでもなく。結果、どちらも生身の人間らしい脆さが感じられます。
低音域の迫力のなさをカヴァーするためなのでしょうか、アレンもヴェヒターもわざと音程を外して、演技過剰に聴こえるのがちょっと残念ではあるんですけれども(モーツァルトのオペラは音楽が心理描写も情景描写も全てカンペキに表現しているので、大袈裟な演技は必要ないと思っているクチ)。
特に、石像が去った後にドン・ジョヴァンニが歌う
「Da qual tremore insolito
sento assalir gli spriti! ……」
あたりの旋律は大好きなので、きちんと聴きたい時にはサミュエル・レイミーのDVDを鑑賞しています(この人が歌うと、石像とタイマン勝負どころか、ヘタすりゃ石像より立派に聴こえマス)。
ヴェヒターも高めのバリトンですね。FDとよく似たドイツ的(?)な歌唱が微妙に気になりますが、底抜けに陽気で、どこか呑気なところもある“ナンパ師”といったキャラクターが好印象。
そういえば、この作品について、私が子どもの頃に抱いていたイメージには、こういうブッファ的な色合いが濃かったように思います。アンナが登場するとちょっと悲劇的な空気になるけど、それ以外ではエルヴィラ、レポレッロを相手にドタバタ、ドタバタ。
ところが、ラストの石像の登場で、物語は一気に暗転する。その劇的な展開に度肝を抜かれたものでした。
なので、幕開けから一貫して不吉な雰囲気を漂わせる演奏や演出は、実はあまり好みではありません。demonicなドン・ジョヴァンニも、試みとしてはおもしろいとは思いますが、レポレッロと早口でまくしたてる旋律がキャラと合わないので、イマイチ気持ちが入っていかないのですね。
というわけで、ドンジョはつやつやしたバリトン希望。バスでも声が明るきゃいいですが、要所要所でずっしりと重く響きますので、軽薄なドンジョのイメージからはちょっとズレてしまいます。
立派なバス声は、クライマックスで石像が聞かせてくれるからいいんデス。
ドンジョに高めのバリトンを望むのは、このクライマックスでの三重唱(ジョヴァンニ、石像、レポレッロ)が最大の“萌えポイント”だからなんですね。
クライマックスの直前まで、華やかで生命力にあふれたパートを歌っているドン・ジョヴァンニ。ところが、石像の登場とともに重厚で不吉な和音に押さえつけられ、たちどころに身動きがとれなくなります。このオペラ全体の楽曲の進行を支配し、操っていた権力が、主人公のジョバンニから石像に移るわけです。
「Parlo: ascolta! piu tempo non ho! (I will speak. Listen. My time is short!)」
と歌う石像のパートが、ティンパニ付きの、大音響の管弦楽に後押しされているのに対し、
「Parla, parla, ascoltando ti sto, (Speak then, for I am listening,)」
ジョバンニのパートの伴奏は弱々しい弦楽器と木管だけ。
うわ言のようなレポレッロのパートでさえ、2回目は石像のパートのほうに重なっていますので、この部分でのジョバンニは、どんなに気丈そうな歌唱であっても、哀れで、処刑台の前に独り立たされた者のような危うさが感じられると思うのです(モーツァルトって、やっぱ凄い)。
「オトコが痛めつけられ憔悴する図」に萌えるワタシとしては、できればここで、石像とタイマン勝負してほしくない。意地を張ろうと強がろうと、声の力と迫力では圧倒的に石像に劣っていてもらいたい……というのが、ワタシの理想のジョヴァンニ像。ハイ・バリトンなら、そのような雰囲気は顕著に出やすい(と思います)。
ただでさえ石像に抵抗する部分のジョバンニの旋律はキーが低め。バス歌手ならキレイに発声できますが、これが例えばアレンだとちょっと嗄れて聴こえます。アレンに比べれば低めの音域も得意そうなヴェヒターも、この録音ではさほどでもなく。結果、どちらも生身の人間らしい脆さが感じられます。
低音域の迫力のなさをカヴァーするためなのでしょうか、アレンもヴェヒターもわざと音程を外して、演技過剰に聴こえるのがちょっと残念ではあるんですけれども(モーツァルトのオペラは音楽が心理描写も情景描写も全てカンペキに表現しているので、大袈裟な演技は必要ないと思っているクチ)。
特に、石像が去った後にドン・ジョヴァンニが歌う
「Da qual tremore insolito
sento assalir gli spriti! ……」
あたりの旋律は大好きなので、きちんと聴きたい時にはサミュエル・レイミーのDVDを鑑賞しています(この人が歌うと、石像とタイマン勝負どころか、ヘタすりゃ石像より立派に聴こえマス)。



